稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

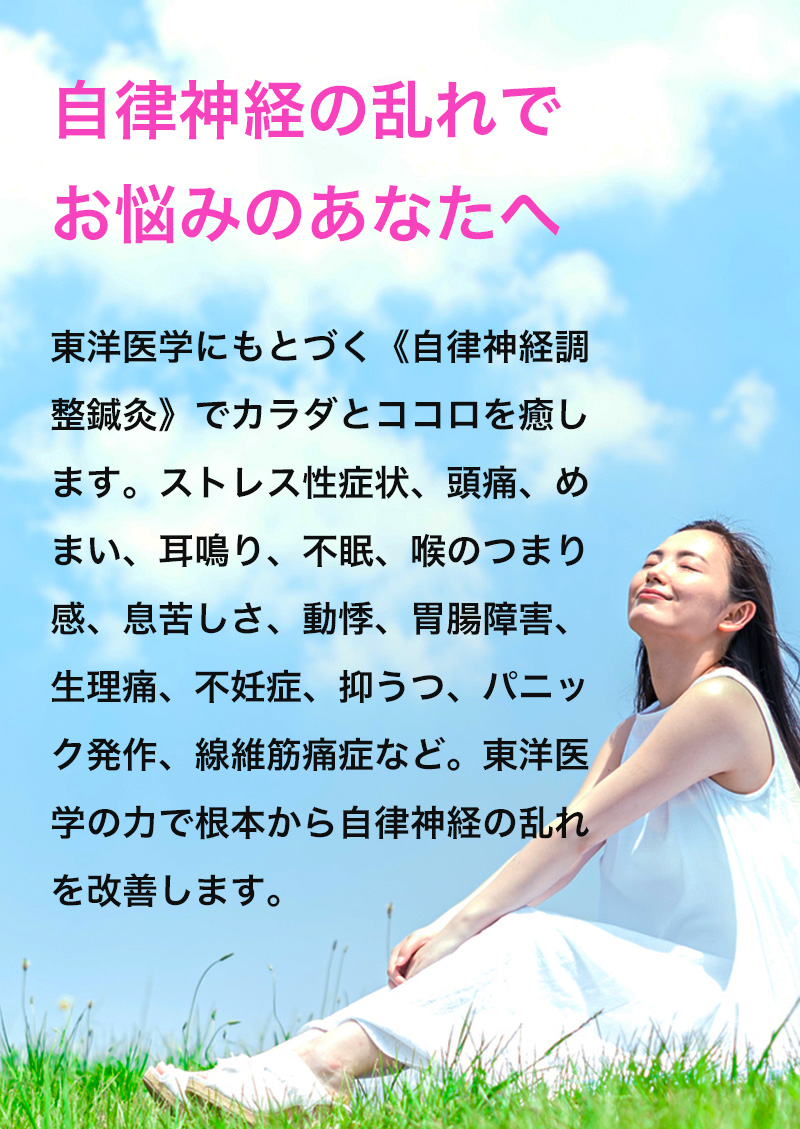

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
自律神経は循環、呼吸、消化、発汗・体温調節、内分泌機能、生殖機能、代謝など、意識ではコントロールできない体の働きをコントロールしています。自律神経には交感神経と副交感神経があり、双方のバランスで生体機能の恒常性を保っています。
自律神経は精神とも密接に関わっていて、精神的ストレスが自律神経を乱すことがあります。また外気で体を冷やすこと、冷たいものを常食すること、昼夜逆転の生活、怪我などでも乱れます。自律神経が乱れると動悸、息苦しさ、吐き気、便秘・下痢、冷え・発熱など、多様な症状が出現する可能性があるのです。
では当治療室の自律神経失調症の症例をご紹介します。高校2年生の16歳の男子が母親に付き添われて来院されました。高校2年生に上がってから食欲がなくなり、吐き気、眩暈、頭痛、熱感、不眠症状が現れました。そのことで学校も休みがちだということでした。
病院を受診しましたが、検査で身体には特に問題がないとのことで、うつ症状と診断されました。病院からはドグマチールやソラナックスが処方され、2か月ほど服用していましたが症状の改善がみられませんでした。
当治療室で問診すると、小学校5年生の時にインフルエンザに罹り、それ以降体調を崩していたことが分かりました。そしてインフルエンザが治っても腹痛が治らずに、結局6年生に上がったものの、1年間登校できなかったのです。
体を診ると、体幹部はほのかに発熱している状態でしたが、下肢は完全に冷え切っていました。特徴的なのが腹部で、お臍の左に大きなコリがありました。どうもこのお腹のコリが自律神経を乱して多様な症状を出している原因のようでした。
治療は冷えている内臓を背部のツボを使って整えることにしました。週2回ほどの治療を行い、4回ほどでお臍の左のコリが緩んでくると、主だった症状が徐々に消えていきました。
しかし食欲が今一つ戻らず、またお腹のコリも完全には無くなっていないことから、鍉鍼(ていしん)という刺さない特殊な鍼で直接コリを処置したところ、食欲が一気に出てきて他の症状も完全に無くなりました。
約2カ月に渡る11回の治療でしたが、最後の治療日に会った時には、テニスで真っ黒に日焼けして精悍な青年になっていました。初めて来院された時の青白い、今にも倒れそうな姿が想像できないほどでした。
さてこの症例のように、胃腸は自律神経と密接な関係があります。この症例ではインフルエンザがきっかけで腸に問題が生じ、自律神経が乱れて多様な症状で苦しんでいました。病院で処方されたドグマチールやソラナックスが効かなかったのは、このような病変が腸にあったためと考えられます。自律神経が乱れる原因は多様です。詳細な問診と丁寧な体表観察で病の原因を正確に捉えることが大切なのです。
逆子とは、お腹の中で赤ちゃんの頭が上になっている状態のことをいいます。医学的には「骨盤位」と呼ばれています。多くの場合、妊娠32〜36週ごろには自然と頭を下にしてくれますが、中には出産の直前まで逆子のままのこともあります。
もし出産時に赤ちゃんが逆子の状態だと、帝王切開になる可能性があるため、心配される方も多いかもしれません。
現代医学では、逆子になるはっきりとした原因はまだ分かっていません。双子などの多胎妊娠、子宮のかたちや筋腫、胎児の未熟性、羊水の量、胎盤の位置など、いくつかの要因が考えられています。
一方で東洋医学では、「お母さんの体の状態が赤ちゃんに映し出される」と捉えます。赤ちゃんはお母さんの一部であり、心と体のバランスがそのままお腹の中にも反映されると考えるのです。
特に、赤ちゃんの位置と深く関わるのが“腰”。生殖器にもつながる腰椎がゆがんでいたり冷えていたりすると、赤ちゃんが回転しづらくなることがあります。
また、東洋医学的に見て逆子になりやすい体質としては、
鍼灸では、体の巡りを整え、赤ちゃんが自然に回転しやすい状態をつくっていきます。特によく使われるのが、足の小指にある「至陰(しいん)」や、内くるぶしの上にある「三陰交(さんいんこう)」というツボです。これらのツボは、下半身を温めて、骨盤や子宮周りの血流を促す働きがあります。
当治療室では、お一人おひとりの体質を丁寧に見極めながら施術を行っています。状態によっては、たった1回の施術で赤ちゃんが回ってくれることもありますが、骨盤のゆがみが強い場合は週に1回程度の継続治療をおすすめすることもあります。
鍼灸は、出産が近づいてからでも受けていただけますので、安心してご相談ください。
冷えは逆子の大きな原因のひとつと考えられます。特に、足首・膝・首・肘などの関節部分を冷やさないように心がけてみてください。
また、骨盤を柔らかく保つためには、のんびり気ままなお散歩もおすすめです。荷物を持たず、ただ歩くだけでも、骨盤の緊張がやわらぎます。
そして、目や頭を使いすぎると、頭の骨がこわばり、その影響で骨盤まで固くなることがあります。スマートフォンやパソコンを控えめにしたり、目を閉じて深呼吸したりする時間も大切にしてください。
出産は、女性にとって命をかけた尊い時間です。だからこそ、産前も産後も、ご自分の心と体をやさしく労わってあげてください。
赤ちゃんとの出会いを、安心して迎えられますように。私たちもそのお手伝いができたら幸いです。
赤ちゃんとの出会いを安心して迎えられるように、丁寧にサポートいたします。
どんな小さなご不安でも、お気軽にご相談ください。
春先になるとぎっくり腰(急性腰痛)の患者さんが増えます。これは気温が温かくなったり冷えたりしながら春に向かう「三寒四温」によって、体が疲れて冷えてしまうためです。
腰の筋肉も冷えて緊張しています。このような状態で腰に負担をかけると「魔女の一撃」でぎっくり腰になってしまうのです。
また気温が上がってくるとどうしても薄着になりたくなりますが、多くの人は三寒四温による疲れが取れていません。体の芯は冷えているのです。ですから性急に薄着になるのは良くありません。体の芯が温まるまで薄着は控えた方が無難です。
冷えた飲食も体を内側から冷やすため良くありません。温かくなってきた春先は冷たい飲食よりも、むしろ温かいものを摂った方が良いのです。
東洋医学では体を冷やす邪気を「寒邪(ふうかん)」といいます。春先は風が強くなりますが、風に当たると体は冷えます。これを「風寒」といい「カゼ」を引く原因になります。春先は風寒の邪が体に入りやすい時期なのです。
この時期に「風寒」が体に入るとカゼっぽくなり筋肉は冷えて緊張します。これがぎっくり腰を引き起こします。またこの時期の寝違いも同様です。朝起きてみたら首が痛くて回らなくなることがありますが、それは風寒の邪に入られたことの結果なのです。
このような状態で無理にストレッチや運動などをすると、かえって悪化することがあります。また痛む部位を指圧しても同じように悪化することがあります。こじらせると患部が炎症を起こして長引いてしまいます。ですからぎっくり腰だと思ったら、すぐに専門家に相談すると良いでしょう。
ぎっくり腰の鍼灸治療は比較的シンプルです。風寒の邪を鍼で抜いて、お灸などで体の芯の冷えをとるだけです。すると冷えた体は血液やリンパ液の循環を取り戻し、体が温まっていきます。その結果、強張った筋肉は緩み痛みが減少していきます。
早いと数日で、遅くても一週間以内には全快することが多いです。しかしこじらせてから鍼灸治療をすると時間がもっとかかってしまいます。また無理をすると、場合によってそのまま慢性腰痛になることもあります。ですから腰に異状を感じたら早めに治療をされると良いでしょう。やはり早期発見、早期治療が大切です。