稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

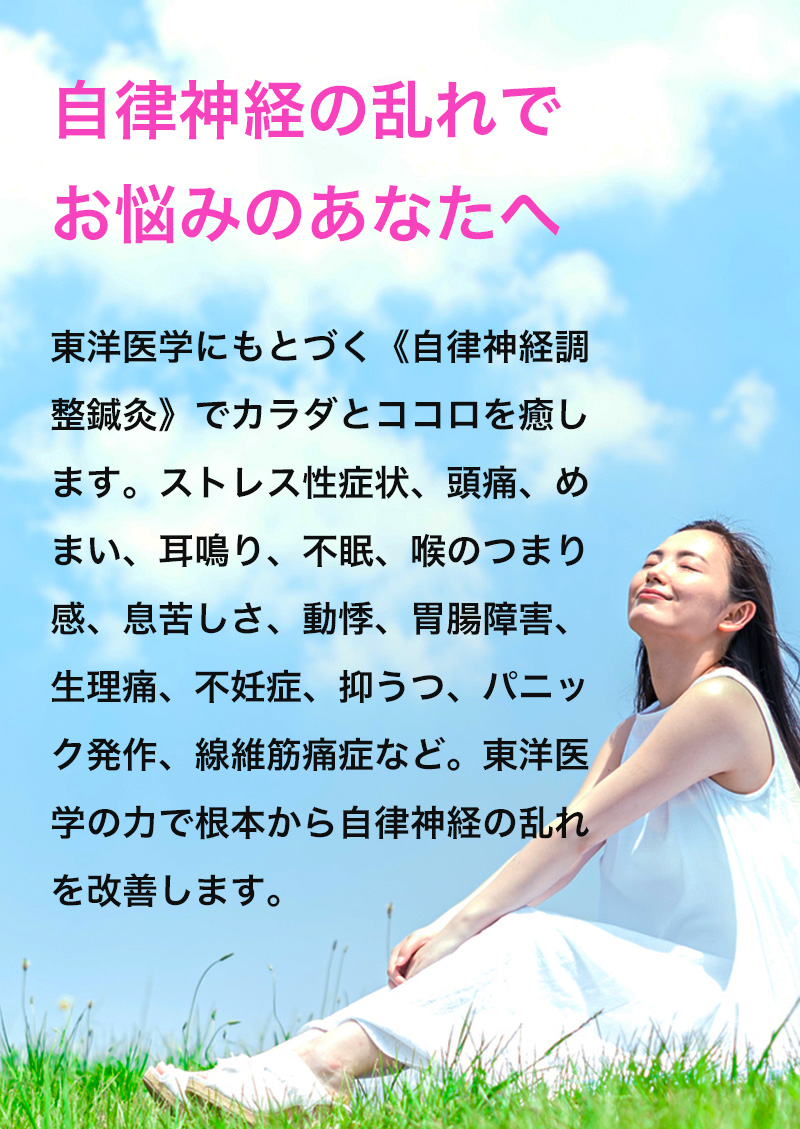

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
第2話 「気」とは何か――病はどこで生まれるのか
遠隔外気功の仮説を成立させる鍵となるのが、「気」という概念である。
気はしばしば、
「見えないエネルギー」
「非科学的な言葉」
として扱われる。
しかし東洋医学において、気は単なる比喩ではない。
それは、身体・感情・環境・関係性を同時に扱うための、実践的な概念だった。
気は量ではなく、状態である。
こうした言葉は、エネルギー量の増減では説明しきれない。
むしろ気とは、
身体と世界のあいだに成立する「関係の場」と考えたほうが近い。
重要なのは、気が意識に応答するという点だ。
注意の向け方、イメージ、意味づけによって、気の流れは変わる。
この視点から見ると、病は次のように捉え直される。
遠隔外気功とは、壊れた部品を修理する行為ではない。
乱れた秩序に対して、整う方向性を提示する行為である。
だからこそ、治療は操作ではなく、共鳴として起こる。
同じ刺激を与えても、反応が人によって異なるのは、そのためだ。
次回は、第3話 意識が世界に触れるとき――人間と宇宙の再定義
冬は秋に引き続き、冷えと乾燥に気をつけましょう。
神経を使い過ぎず、目を労ることも大切です。
「冬」という言葉の語源には、「殖ゆ(ふゆ)」=生命が増え、育まれるという説があります。
これは、もっとも有力とされる語源の一つです。
冬はただ寒く、活動が止まる季節ではありません。
草木の種子や動物の命が、春に向けて土の中でエネルギーを蓄え、増えていく時期。
表に現れないところで、生命は静かに準備を進めています。
冬になると、身体では骨盤が締まり、気やエネルギーが外に広がらず、内側に凝縮していきます。
この内に集められたエネルギーこそが、春に芽吹く力、動き出す原動力になります。
また、エネルギーが分散しにくくなるため、頭部に気が昇りやすく、集中力や思索が深まるのも冬の特徴です。
北の寒い地域では、内向的で思索的な文化が育ちやすく、南の温暖な地域では、おおらかで開放的な気質が育ちやすい。
これは単なる気質の違いではなく、気やエネルギーの向かう方向の違いとも考えられます。
冬は、外に向かうよりも内側を見つめる季節。
考えごとや探究に向いている一方で、神経が昂ぶりすぎると、心配や不安がぐるぐる巡りやすくなる側面もあります。
冬は骨盤が締まり、頭や首も緊張しやすくなります。
この状態のまま春を迎え、骨盤が開こうとする時に頭が強く締まっていると、身体はバランスを取るために不調を通して調整を始めます。
• 頭痛
• カゼ
• 花粉症
これらは「頭をゆるめるための反応」として現れることもあります。
だからこそ、冬のうちから頭・首をゆるめておくことが大切です。
目を酷使しない、しっかり休ませることも重要なケアになります。
冬は空気が乾燥しやすく、その影響で体調を崩しがちです。
• カゼ
• むくみ
• 喉の痛み
• 頭痛
• 肩こり
• 冷え
• 関節や筋肉の痛み
これらの背景には、体内の潤い不足があります。
喉が渇く前から、こまめな水分補給を心がけましょう。
冬は、動かない季節ではありません。内側で殖え、蓄え、整える季節です。
頭と首をゆるめ、目を休め、潤いを保つ。
そうして整えられた身体は、春に自然と、無理なく開いていきます。
冬を丁寧に過ごすことが、次の季節を軽やかに迎える一番の準備になります。
遠隔外気功という言葉を聞くと、多くの人は懐疑的になるだろう。
気功師が、遠く離れた患者に対して、触れることなく、
イメージや意識のみで「気」を送り、病を癒す。
現代科学の枠組みで説明しようとすれば、ほとんど不可能に見える。
もちろん、遠隔外気功は科学的に証明されていない。
だがここでは、是非や真偽をいったん保留し、ひとつの仮説として受け取ってみたい。
もし、遠隔外気功が成立しているとしたら、
私たちの世界は、どのような構造を持っているのだろうか。
この問いは、代替医療の話にとどまらない。
それは、距離とは何か、身体とは何か、意識とは何か、
という根源的な問いへと私たちを導く。
遠隔で作用が及ぶということは、少なくとも次のことを意味する。
このとき、私たちが慣れ親しんできた
「物質が先にあり、意識はその結果として生まれる」
という世界観は、最下層では成立していないことになる。
ここから、世界は次のような三層構造を持つのではないか、という仮説が立ち上がる。
遠隔外気功とは、意識が気の層に働きかけ、
その変化が物質として現れる現象だと考えられる。
空間や距離は、
物質を理解するための一つの見方にすぎず、
より深いレベルでは、世界は連続した場として存在しているのかもしれない。
次回は、第2話 「気」とは何か――病はどこで生まれるのか