稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

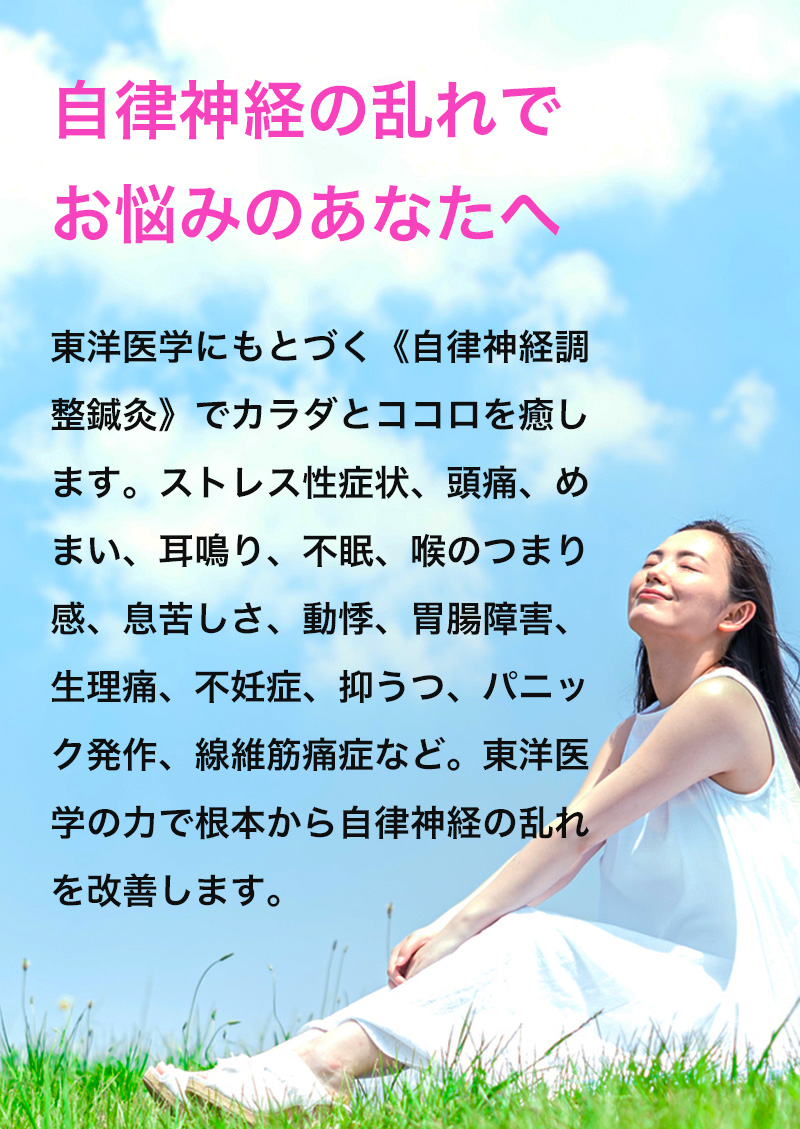

自律神経の乱れによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)は、放っておけば治ると思われがちですが、実は適切な時期に適切なアプローチをしないと、回復が遅れたり可動域が制限されたりすることも少なくありません。
今回は、五十肩の経過を3つのステージに分け、それぞれの時期に合わせた治療法、そして「なぜ鍼灸治療が効果的なのか」を解説します。
五十肩は、一般的に「炎症期」「拘縮(こうしゅく)期」「回復期」の3つの段階を経て回復に向かいます。
痛みが最も強く、何もしていなくても疼く(安静時痛)や、夜に痛みで目が覚める(夜間痛)が特徴です。
* 状態: 肩関節の袋(関節包)に強い炎症が起きています。
* 治療のポイント: 「安静」と「消炎」。無理に動かさず、炎症を抑えることが優先です。
激しい痛みは落ち着いてきますが、肩が固まって動きが悪くなる時期です。
* 状態: 炎症のダメージにより関節包が縮み、癒着して「フローズンショルダー」と呼ばれる状態になります。
* 治療のポイント: 「温熱」と「可動域の改善」。痛みの出ない範囲で少しずつ動かし始めます。
肩の動きが徐々にスムーズになり、痛みがほとんど消失していく時期です。
* 状態: 組織の柔軟性が戻り始めます。
* 治療のポイント: 「積極的なリハビリ」。筋力を戻し、以前の可動域を取り戻します。
鍼灸治療は、西洋医学のリハビリや薬物療法と非常に相性が良く、回復を早めるサポートができます。
| ステージ | 鍼灸のアプローチ | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 炎症期 | 痛みのゲートコントロール、消炎のツボ(曲池など)への刺激 | 夜間痛の緩和、鎮痛効果による睡眠の質向上 |
| 拘縮期 | 深部の筋肉への刺鍼、温灸による血流促進 | 筋肉の緊張緩和、関節の可動域拡大 |
| 回復期 | 全身のバランス調整、弱った筋肉への電気鍼刺激 | 再発防止、肩甲骨周りの機能回復 |
五十肩の痛みは、肩の深い場所にあるインナーマッスル(回旋筋腱板)で起きていることが多いです。マッサージでは届きにくい深層の組織に対して、鍼は直接アプローチできるのが最大の強みです。
Point: 炎症期に無理なストレッチをすると逆効果ですが、鍼灸なら「触れられるのも痛い」状態でも、手足のツボを使って遠隔的に痛みを和らげることが可能です。
五十肩は「いつか治る」と我慢しがちですが、放置すると肩が上がらないまま固まってしまうリスクもあります。
今の自分の肩がどのステージにいるのかを見極め、適切なケアを組み合わせていきましょう。鍼灸は、あなたの肩が再びスムーズに動くための強力なサポーターになります。
「私の肩の痛み、今はどの時期?」と不安な方は、まずはチェックから始めてみませんか?
具体的なセルフケア方法や、あなたの症状に合わせた鍼灸の通い方について詳しくご提案させていただきます。
近年、アルツハイマー病は「脳の糖尿病」とも呼ばれるようになっています。
これは、脳内で起こるインスリン抵抗性が、神経細胞のエネルギー代謝を妨げるという研究に基づく考え方です。
この視点は、生活習慣の改善だけでなく、脳の血流や神経機能に直接アプローチする頭皮鍼治療の意義を考えるうえでも重要なヒントを与えてくれます。
「3型糖尿病」とは正式な病名ではありません。
これは、アルツハイマー病を“脳で起こるインスリン抵抗性”として捉える仮説です。
脳は大量の糖を必要とする臓器ですが、インスリンの働きが低下すると、
• 神経細胞が糖を取り込めない
• エネルギー不足で細胞が弱る
• 記憶を司る領域が萎縮する
といった変化が起こります。
さらに、アルツハイマー病の特徴であるアミロイドβの蓄積にも、インスリン代謝が関与していると考えられています。
頭皮鍼は、頭皮上の特定領域を刺激することで、脳血流の改善と神経活動の調整を目的とする治療法です。
研究では、頭皮鍼刺激が
• 前頭葉や海馬周辺の血流を高める
• 神経可塑性を促進する
• 認知機能の維持を助ける
可能性が示唆されています。
脳の代謝が低下している状態では、血流と神経ネットワークの活性化が重要です。頭皮鍼は、生活習慣改善と並行して行うことで、脳の機能回復を多角的に支える手段になり得ます。
東洋医学では、思考や記憶は「脳」だけでなく、全身の気血の巡りと関係すると考えます。
血糖コントロールの乱れは、
• 微小循環の低下
• 慢性炎症
• 神経伝達の不調
を引き起こし、結果として認知機能に影響します。
頭皮鍼による局所刺激は、これらの循環障害を改善し、脳のエネルギー利用効率を高める補助的役割を果たすと解釈できます。
1. 血糖値スパイクを防ぐ食事
精製糖質を控え、食物繊維を先に摂ることでインスリン負荷を減らします。
2. 1日20分の有酸素運動
運動は脳由来神経栄養因子(BDNF)を増やし、神経細胞を保護します。
3. 良質な睡眠
睡眠中に脳の老廃物が除去されます。6〜7時間以上を目標に。
4. 頭皮への物理的刺激
セルフマッサージや定期的な頭皮鍼は、血流改善と神経活性化を助けます。
アルツハイマー病を「脳の糖尿病」と捉えると、認知症は単なる加齢現象ではなく、代謝と循環の問題として理解できます。
食事・運動・睡眠という基本習慣に加え、頭皮鍼による神経刺激を組み合わせることで、脳の健康をより積極的に支えることができます。
10年後、20年後の明晰な思考を守るために、今日からできることを一つずつ始めてみましょう。
まだ寒さが残っていますが、私たちの体はすでに春に向けて変化を始めています。
自然界のリズムと同じように、体も季節に合わせて動いているのです。
秋から冬にかけて、体はエネルギーを内側に蓄えるモードに入ります。
骨盤は徐々に閉まり、エネルギーを収斂させながら、寒い季節を乗り越える準備をします。
この時期にしっかりと内側でエネルギーを養うことが、春の活動期の土台になります。
そして春になると、体は一気に発散の方向へと転じます。
骨盤が開き始めるのに伴って、肩甲骨や頭蓋骨の動きも活発になります。
体内のエネルギー循環が良くなり、気の巡りがスムーズになるのがこの季節の特徴です。
この「巡りが良い状態」は、慢性的な不調の改善にとても適しています。
体が変化を受け入れやすく、調整に対する反応も出やすい時期だからです。
特に不妊症の場合、骨盤や腰椎の硬さ、冷え、歪みが関係しているケースが多く見られます。
春の自然な開放の力を利用して体を整えていくことで、より良い結果につながりやすくなります。
すでに婦人科で不妊治療を受けている方にとっても、東洋医学の視点から体の構造やバランスを整えることは大きな助けになります。
西洋医学の治療と並行して行うことで、体全体の状態を底上げすることができるからです。
春という変化の季節をきっかけに、東洋医学による鍼灸治療を取り入れてみてはいかがでしょうか。
体が本来持っている力を引き出し、妊娠しやすい土台を整える良い機会になります。
鍼灸には、あなたの本来の力をそっと引き出す力があります。
ご一緒にできることを探してみませんか?
またはお電話でのお問い合わせも承っております。
📞 047-301-9015(日曜・月曜定休)