稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

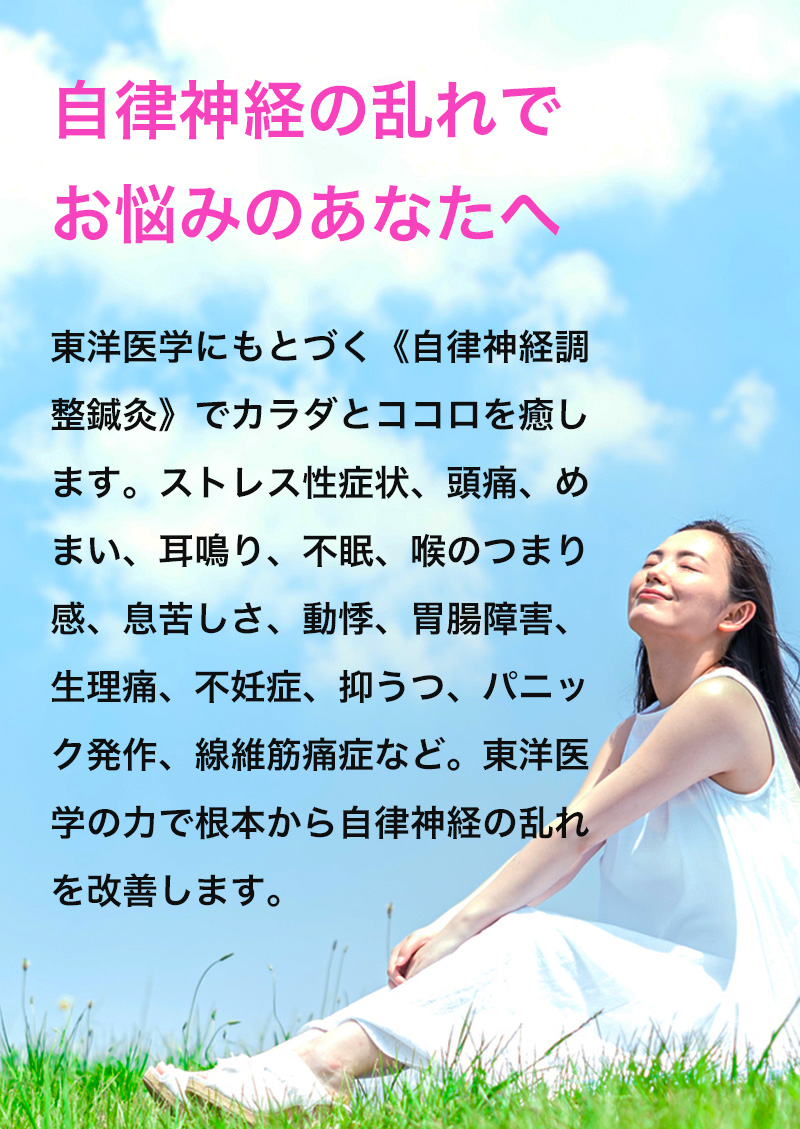

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
もうすぐ6月。梅雨入りの時期ですね。
湿度が高まることで呼吸器、泌尿器、消化器に負担が掛かり、身体的にどこか重苦しい状態になります。
プラナの常連さんにはそれぞれのエネルギーラインを活性化させて、梅雨が楽に越せるようにしています。
梅雨の時期は小食、適度な運動(発汗)、水分補給などが重要です。
詳しくは下記の記事を御覧ください。
いつもプラナ松戸治療室をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
当治療室は3/27(火)に移転致します。
場所は京成松戸線八柱駅・JR武蔵野線新八柱駅南口から徒歩3分で、
県道281号線沿いの「カーザ日暮」ビルの505号室です。
一階に「古都錦堂」という仏具店があります。
【マップ】

【アクセス】

1. JR武蔵野線新八柱駅・京成松戸線八柱駅の南口ロータリーに出ます。

2. 交番とauショップ、セブンイレブンの間の道を通ります。

3. 道なりに歩きます。

4. 道なりに歩くと・・・、

6. 県道281号線に出ますので、歩道を渡ります。

7. 歩道を渡ったら右へ、県道沿いを松戸方面に向かいます。

8. 数十秒ほど歩くとグラデーションの外壁のビルが見えてきます。そのビルが目的地です。

9. 到着です。

10. 「505」号室を呼び出して下さい。
新住所:千葉県松戸市日暮3-10-10 カーザ日暮505号室
※ 移転先での診療は3/27(火)からになります。
※ 電話番号が3/26(月)に変更になります。
3/26になりましたら当治療室サイトの電話番号を変更致します。
それまでは現在の番号で通じます。
1. はじめに
パニック障害の方のカラダとココロには特徴があります。カラダもココロも強張りが強く、弾力性が乏しいのです。この特徴にうまく対処できると、パニック発作を起こす頻度が大幅に減ったり、症状が出なくなります。以下にその特徴を述べます。
2. カラダの特徴
パニック障害の方は精神的な緊張のために強くカラダが強張り、血液循環が悪くなって冷えている傾向があります。東洋医学で「肝鬱」と呼ばれる状態で気血の巡りが悪く、逆上せて首、肩、みぞおち、上部腰椎が硬くなっています。自律神経の交感神経が優位な状態です。
このような状態ですから普段からどことなく体調が優れず、パニック発作を以前起こした場所、例えば電車や会議室、映画館、飲食店などに行こうとするだけで敏感にカラダが反応してさらに強張り、予期不安と呼ばれる動悸や吐き気、冷や汗などの自律神経症状が出やすくなります。
このような状態を改善するにはカラダの緊張をほぐして気血の循環を促すことが大切です。改善方法は適度な運動をすることです。あまり激し過ぎない運動を選ぶことが大切です。
例えば気功、太極拳、ヨガなどのゆったりとしたエクササイズを気長に実践するとよいでしょう。もちろん鍼灸治療で体を整えることもとても効果的です。このような運動を続けることで気血が巡るようになり、カラダが温かくなり弾力性も出てきます。また下腹部にある「下丹田」が充実してきて、いわゆる「肚が据わる」状態になり、精神的にも落ち着いてきます。

3, ココロの特徴
パニック障害になる方は完璧主義で他人に自分の弱みを見せられない傾向があります。体調が悪くなっても、なるべく人に悟られないように繕ろいます。その虚栄心がさらにココロを緊張させるのです。
完璧主義で人に弱みを見せられないのは劣等感が強いためです。劣等感は決して悪い感情ではなく、向上心を生む力になります。しかし自分の劣等感を認められず、他人にも決して悟られないように優秀な人物を演じようとすると、常に神経を緊張させながら生きることになりるのです。
完璧さを求める傾向は他人にも向けられ、人のミスに対しても寛容さがなくなります。そのせいで人からすると常にどこか緊張感を感じさせることになり距離感を生みます。それが疎外感や孤独感を感じる原因になるのです。
この性格を改善させるには自分の劣等感を認め、必要な時には他人にも開示することです。そうすることで楽に生きることができるようになります。この世に完璧な人はいません。虚勢を張らずに自分や他人の不完全さを許すことです。
また他人があなたにそれほど関心がないことも理解すると良いでしょう。人が最も興味があるのは、あなたではなく自分自身のことです。あなたに一時的に注目が集まることはあっても、すぐに忘れて別の話題に移るのが世の常です。自意識過剰を捨てて、ありのままのあなたで生きることが大切なのです。

4. まとめ
以上がパニック障害の方のカラダとココロの特徴です。カラダの強張りを緩めて気血を巡らし、劣等感を前向きに捉え、時に自分の弱みを他人に開示します。人間の不完全さを受け入れ、自他を許し、ありのままの姿で生きることが大切なのです。改善方法を上手に取り入れ、カラダとココロに弾力性を取り戻して、ぜひパニック障害を克服して下さい。