稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

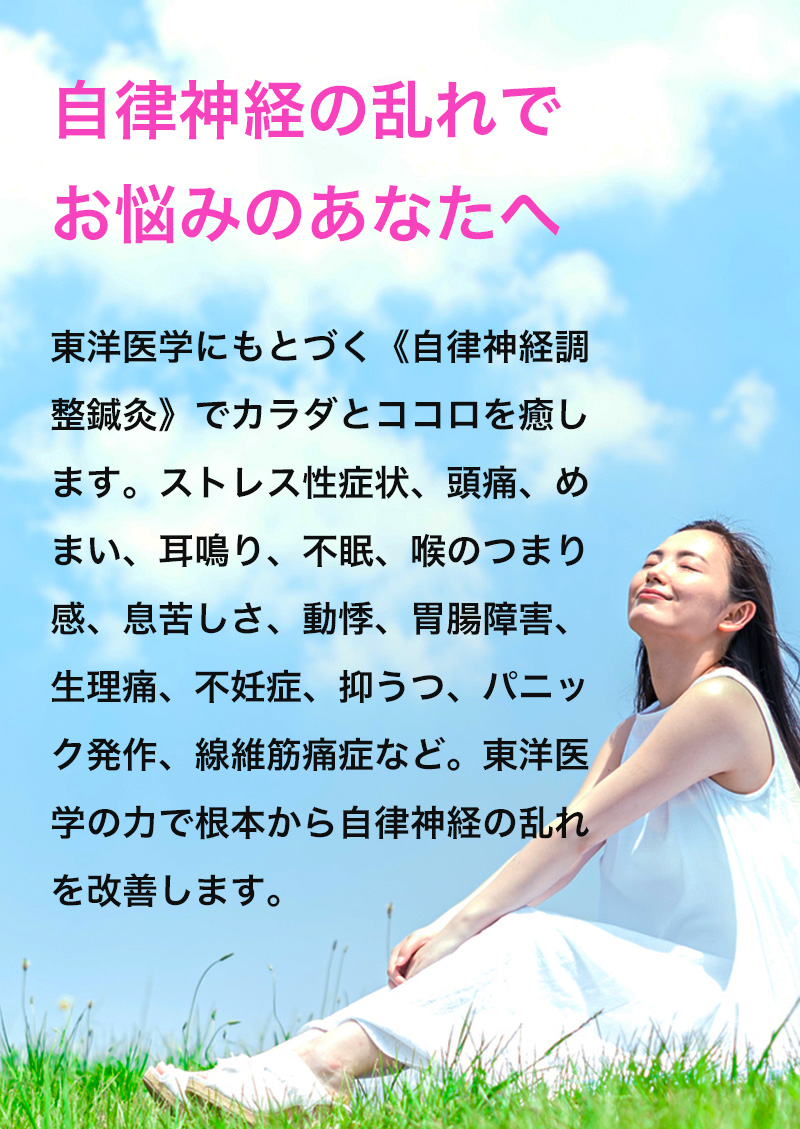

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
腎臓内科に長く勤務しているある医師は、街中で人の後姿を見ていると、
そのひとが腎臓の病に冒されているか否かを判断できるといいます。
洋服の上から判断出来るということで、どうも普通の診方ではないようです。
多分その医師は、オーラを診断しているのではないでしょうか。
もちろんその医師が、知的には霊性の世界を理解していないかもしれません
が。
私たち東洋医学を学ぶ者たちも、患者さんのオーラを診る訓練をすることがあ
ります。いわゆる「望診 ぼうしん」と呼ばれるもので、患者さん全体の雰囲
気や顔の気色を診たりします。
なかなか重宝な診断で、例え今症状がそれほど変化していなくても、治療後に
望診で良い状態であれば、今後症状が好転していくことが予想できるのです。
もちろん予後の診断は、その他にもろいろあるわけですが・・・。
では見方ですが、オーラは体の周りを覆っているので、体の少し前あるいは後
に焦点を合わせます。肉体の方は少しボヤケタ感じです。そのように見ると、
体の周りに陽炎のようなモヤモヤが見えてきます。場合によっては色が見えて
くるかもしれません。顔の望診をする時も、顔の少し前に焦点を合わせます。
始めは練習として、自分の両手の指先を、近づけたり離したりして、指先のオ
ーラを見る訓練をするといいでしょう。背景は黒か白が見やすいと思います。
このような見方ができると、ひとは目に見えるものだけではなく、目に見えな
いものにも影響を受けて生きていることを知るようになり、人や環境に対して無
関心ではいられなくなるのです。人生の視野が広がります。
プラナ松戸治療室 http://prana502.hp.infoseek.co.jp/
職場で苦手なひとがいて、顔を合わせるのが憂鬱になるといったことはありませんか?
会社勤めの方にはよくある問題だと思います。では何故そのひとが苦手なのでしょうか。
心理学では、それは自分の性格の認めたくない部分(シャドウ)をその人物に投影してい
るからだといいます。
つまりその苦手な人の嫌な部分を実は自分が持っていて、それを無意識的に嫌っているわ
けです。
ではシャドウを無くすにはどうしたらいいのでしょうか?
なかなか難しい問題ですが、私は「お祈り」を勧めています。
その苦手なひとが誰よりも幸せになるように、就寝前の数分間祈るのです。
相手の姿をイメージして、その人がニッコリと微笑むくらいまで祈ります。
この行為はひとの幸福を祈る尊い行いであると同時に、自分のシャドウを赦す行為でもあ
るのです。
不思議なことにこの行為を継続して行うと、自分が変わっていくだけでなく、相手の態度
も変化していくことに気が付きます。
またさらに不思議なことには、自分、あるいは相手が突然異動になったり、別の事態で顔
を合わせる機会がなくなるなど、自分を取り巻く環境が大きく変化していくのです。
自分を見つめることをせずに、相手を責めている場合、いつまでたっても同じような状況
が繰り返し起こります。
どうも早いうちに気が付いて、自分の心を見つめた方が得策のようです。
プラナ松戸治療室 http://prana502.hp.infoseek.co.jp/
この頃周りを見渡せば、マスクをしている人があっちにもこっちにも。
花粉予報によれば、今年は前年並みの少なさだということでしたが、周りの状況を見る限
りそうでもないようです。暖冬が災いして、早期に大量に飛んでいる様子。
今期の総量としては少ないのでは?とも言われていますが、どうなんでしょうね。
花粉症になる方は首や肩が異常に張っていて、血流が悪い方が多いようです。
顔や鼻に分布する血管に悪影響を与えて、炎症が起きやすい環境になっているのでしょう。
首や肩の張りを改善すると、途端に鼻や目が楽になってくることからそれが推察されます。
食事内容も影響が大です。辛いもの、刺激が強いもの、お酒など熱性が強い食品は控えた
方が無難です。
花粉症の原因はアレルギー反応ですが、体の構造に歪みがあると、さらに悪化するようで
すので、鍼灸や整体でケアされるといいですよ。
プラナ松戸治療室 http://prana502.hp.infoseek.co.jp/