稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

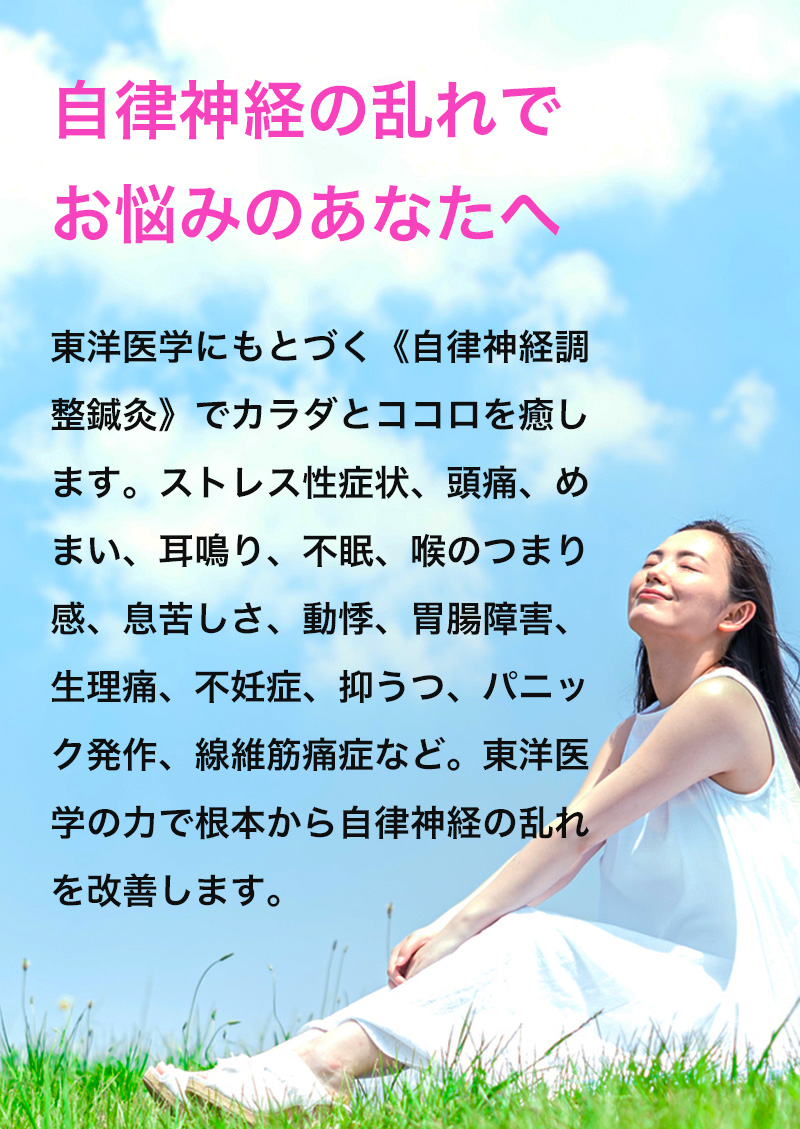

自律神経の乱れによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
現代では「HSP(Highly Sensitive Person)」=「神経過敏な人」という概念が広く知られるようになりました。HSPとは、生まれつき感受性が強く、五感や情緒に対して人一倍敏感に反応する気質を持った人のことです。人口の約15〜20%に存在するとされており、決して珍しいものではありません。
これらの特徴は、単なる「繊細さ」ではなく、脳の感覚処理システムが深く複雑であることが関係していると考えられています。研究によれば、共感や感情認知に関わる脳領域が通常よりも活発に働いていることがfMRIで確認されています。
感受性の高さには遺伝的傾向があり、神経伝達物質(特にセロトニン)に関連する遺伝子型との関連が報告されています。また、幼少期の環境(養育、トラウマ、愛着)によって発現の仕方が変わる「感受性の両義性」も重要なポイントです。
神経過敏な人にとって、鍼灸治療は非常に効果的なセルフケアおよび身体調整法になり得ます。なぜなら、鍼灸は「交感神経優位」から「副交感神経優位」への切り替えを促し、過敏に反応する神経系を穏やかに整える働きがあるからです。
特に当院では、ただの局所治療ではなく「全身の気の流れ」と「神経の連動性」を重視した施術を行います。脊椎や腹部の調整を通じて、からだとこころの連鎖にアプローチすることで、深いリラックスと自己調整力の回復を目指します。
HSP気質の方にとっては、「どこで、誰と、どう生きるか」が健康と幸福の鍵を握ります。以下のようなライフスタイルが有効です。
現代は刺激過多な社会です。だからこそ、自分の「感受性」をネガティブに捉えず、「繊細さ」という才能として活かしていくことが求められます。鍼灸はその土台づくりを支える有効な手段の一つです。
神経過敏(HSP)は、決して病気ではなく、一つの「気質」であり「才能」です。自分を深く知り、適切なセルフケアや環境を整えることで、創造性と感受性を生かした人生を築くことができます。鍼灸治療は、そのような人生の伴走者として、大きな助けとなるでしょう。
【参考文献】
• Aron, E. N. (1996). The Highly Sensitive Person. Broadway Books.
• Aron, E. N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology.
• Liss, M., et al. (2005). Sensory processing sensitivity and social cognition. Personality and Individual Differences.
• Acevedo, B. P., et al. (2014). The highly sensitive brain: fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others’ emotions. Brain and Behavior.
神経過敏やHSP気質にお悩みの方、からだとこころを整える鍼灸治療に興味のある方は、下記のリンクよりお気軽にご相談ください。
東洋医学に関する最新の科学的研究や、厚生労働省による取り組みをわかりやすくまとめた、非常に観ごたえのある内容です。
特に、鍼灸がどのように体に働きかけて効果を発揮するのか、その仕組みについての解説がとても丁寧で、専門知識がなくても理解しやすくなっています。
なかでも印象的なのが、うつ病患者を対象に行われた治療の比較試験の結果です。
①通常の治療、②通常治療+漢方薬、③通常治療+鍼灸治療の3つのグループに分けて効果を調べたところ、なんと③の「鍼灸を加えた治療」が最も改善効果が高かったというのです。
この結果は、医療関係者の間でも大きな注目を集め、東洋医学の新たな可能性として話題になりました。
私たちは「病気」を、健康な状態からの逸脱、不具合、あるいは克服すべき問題と捉えがちです。
しかしそれは、身体や精神の苦痛という表層的現象にとどまらず、深い存在論的・意味論的メッセージを帯びています。
今回は「病気とは何か?」という問いを、仏教とユング心理学、そして私たちのこれまでの探究──「世界は意味に満ちた応答性の場である」という視点から再考していきます。
仏教では、「病(びょう)」は単なる身体の障害ではなく、無明(真理を知らぬ心)と煩悩(執着)によって引き起こされる苦しみの現れとされます。
『法句経』では、「病あることは苦なり、病なきことは安らぎなり」と述べられますが、これは肉体的な苦痛というより、煩悩によって歪められた世界認識が生む苦を意味します。
つまり、仏教において「病気」とは、心と世界の関係性が偏った状態ともいえるのです。
ユング心理学では、病気──特に神経症やうつ、夢に出てくる病的イメージ──は、単なる障害ではなく、無意識からのメッセージと見なされます。
たとえば、「ある日突然体調が崩れた」という出来事は、表面的には医学的原因があるかもしれませんが、象徴的には“人生の軌道修正”や“抑圧していた感情の爆発”であることもあるのです。
ユングは次のように述べています:
魂の病は、魂が自身を治そうとする努力でもある。
つまり、病は敵ではなく、魂の自己調整機能として尊重されるべき存在なのです。
私たちの問いに「世界が応答する」というこれまでの議論を思い出しましょう。
ならば、「病気」とは、私たちの生き方、関係性、内的な問いかけに対して世界が返す“ひとつの応答”だと捉えることができるのではないでしょうか?
たとえば:
病気になると、私たちは他者に助けを求めるようになります。医師、看護師、家族、友人……そのときに現れる他者は、単なる支援者ではありません。
彼らは、「応答する他者」として、病という孤独の中に差し込む光のような存在です。
また、仏教の菩薩は、病者の苦をわがことのように受け取り、癒そうとする存在です。『維摩経』の維摩居士は、自身が重病でありながらも、病者の心に寄り添い、智慧を語る人物として描かれます。
ユング心理学における「個性化のプロセス」では、人生の危機、病気、喪失などの出来事は、“魂の目覚め”を促す転換点として扱われます。
病気によって、私たちは以下のような変化を経験します:
これはまさに、内面の再構成=個性化を進めるプロセスなのです。
慢性疾患や難病、あるいは末期の病──それは、「死」という究極の問いに直面する場面でもあります。
しかし、仏教においては、病を通じて死と向き合うことが、煩悩を離れ、解脱への道に至る機会であるとも教えられます。
たとえば、『涅槃経』では、病の中でこそ真の仏法が現れると説かれています。
死にゆく過程は、単なる衰退ではなく、魂が意味へと向かって成熟していく旅でもあるのです。
「病」とは何か?
それは、ただの生理的エラーではなく、魂が内なる歪みを修正しようとする叫びであり、世界が私たちに返す“もうひとつの応答”なのです。
仏教が「無明を明らかにし、縁起を観よ」と言うとき、そこには「病を通じて生き方を見直すこと」が含まれているでしょう。
ユング心理学が「症状には意味がある」と語るとき、そこには「病こそが癒しの始まりである」という希望が含まれています。
私たちが病むとき、そこには孤独と苦しみだけでなく、「応答する世界」が静かに私たちに語りかけている声があるのかもしれません。