稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

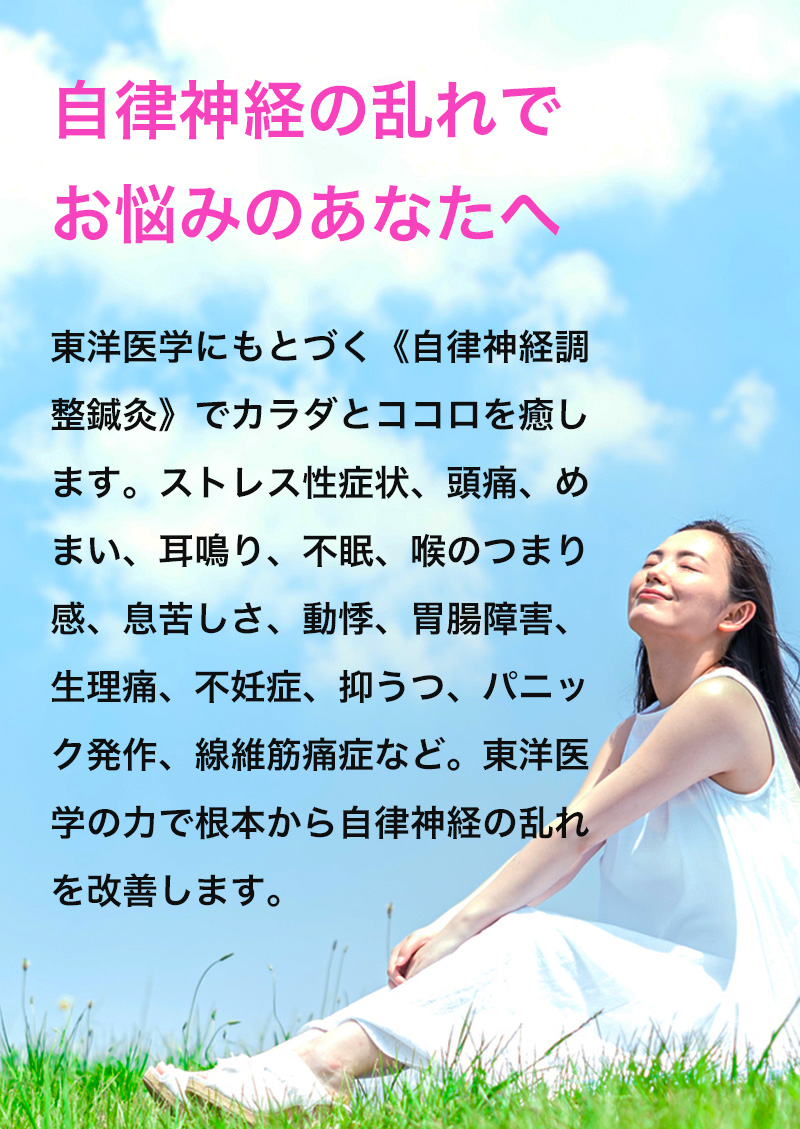

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
先日診た患者さんは、花粉症の症状はないものの、
目の反応点に、かなりの充血反応が現れていた。
ここ20年間で花粉飛散量は3~5倍に増えたそうで、
今年は例年に比べて飛散量は少ないようだが、
昔に比べるとやはり多いに違いない。
花粉症が発症していなくても、目や鼻に異物感を感じている人は
少なくないようである。
対策としては、洗い流すのが手っ取り早い。
涙の味程度の生理食塩水を人肌程度に温め、
目を洗い、鼻うがいを行う。
1日に2回ほど行うといいようだ。
しかし花粉症の原因には免疫機能の問題があり、
それを正常化させる必要がある。
東洋医学的に観れば花粉症の人は「気」が上がり、
頭部に気がこもった状態である。
こまめに鍼灸治療を受けて身体機能を正常化させ、
滞りなく全身に気が巡るようにする必要がある。
花粉症は集中力を低下させ、仕事の質を悪くさせる。
体を整えるのも仕事の内と思われては如何だろうか。
プラナ松戸治療室 https://pranaworks-jp.com/
患者さんたちの脈が、
「春の脈」を打つようになってきた。
東洋医学では、手首の脈で体の状態を診るが、
各季節特有な脈状があり、
その季節の脈を打っていないと
病的な状態だと分かる。
私達は地球、いや宇宙の影響を受けながら
日々生きているのだ。
患者さんの体が春を告げる。
温かくなるのも、すぐそこだ。
プラナ松戸治療室 https://pranaworks-jp.com/