稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

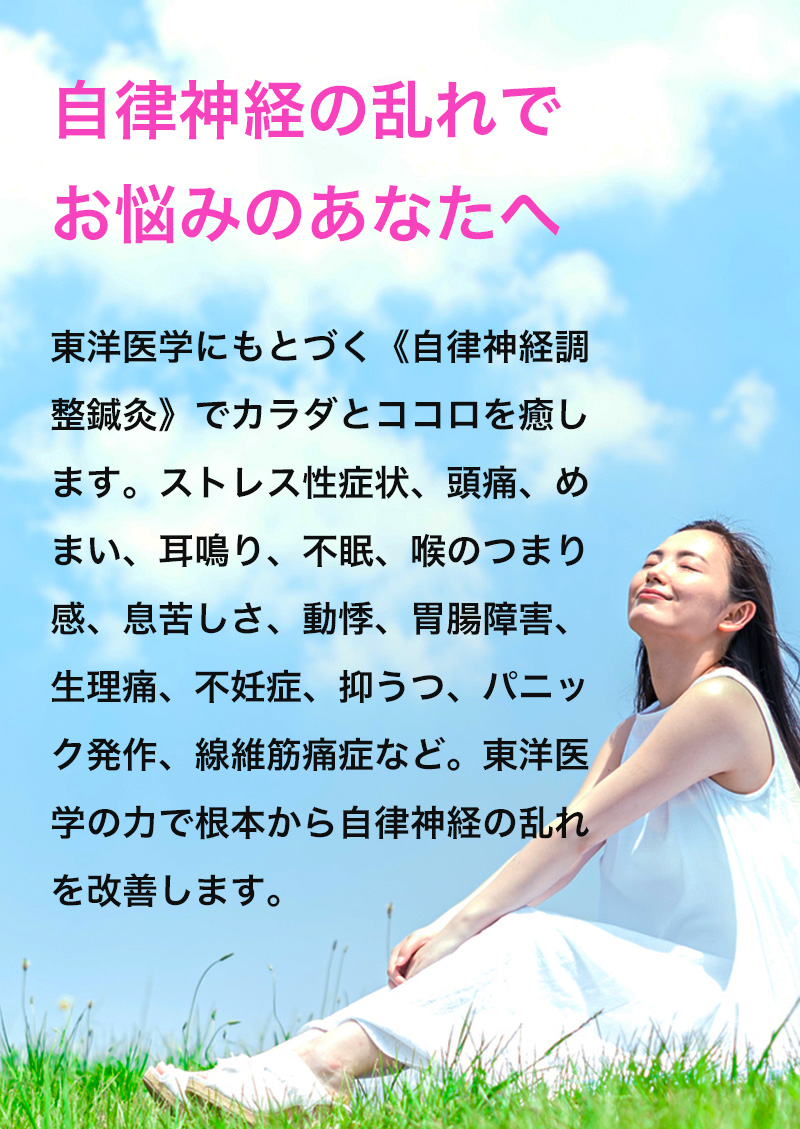

自律神経の乱れによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
私たちは「現代医学は科学的で正しい」と思いがちです。ですが、人類学や科学社会学の視点から見ると、少し違う見え方がしてきます。今回はフランスの思想家 ブリュノ・ラトゥール(Bruno Latour) の考え方をもとに、「医学も信仰である」とはどういうことかを、やさしく解説します。
私たちは「科学は真実を明らかにする」と信じています。でもラトゥールはこう問いかけました。
科学的な“事実”は、研究室という現場で、人や道具やデータのやりとりの中から作られている。
つまり、「これは事実です!」と発表されるものも、実は長い議論や実験、そして社会的な合意の積み重ねによってようやく「事実」として扱われるようになるのです。
たとえば、風邪に抗生物質を出すべきか、がんに標準治療を使うべきか…。
こうした医学的な判断も、「科学的だから正しい」と思われがちですが、
こういった人間社会の都合に大きく左右されています。
ラトゥールの主張の中で印象的なのが、「科学も宗教に似ている」という視点です。
科学も、専門家・実験機器・論文・制度などによる「信頼のネットワーク」によって支えられている。
つまり、私たちが薬や治療を「効く」と感じる背景には、その医師や制度、医学的な世界観を信じているという側面があるのです。
これは現代医学を否定する話ではありません。むしろ、こうした「科学のつくられ方」を知ることで、
を持つことができます。
ラトゥールの問いかけは、科学や医学を「信じる/信じない」で分けるのではなく、もっと深く理解し、使いこなすための視点なのです。
医学も東洋医学も、アーユルヴェーダも、「世界の見方」のひとつです。何を信じるかは、あなた自身が決めていいのです。
文責:プラナ松戸治療室
「最近、やる気が出ない」「眠りが浅い」「なんだか毎日がつらい」——
そんな症状に心当たりのある中高年の男性、もしかするとそれは男性更年期障害(LOH症候群)かもしれません。
あまり知られていないこの症状ですが、実は多くの男性が密かに悩んでいます。今回はその実態とメカニズム、医学的な治療法、そして鍼灸がどのようにお役に立てるかについて、信頼できる情報をもとに丁寧にご紹介します。
LOH(Late-Onset Hypogonadism)症候群とは、加齢によって男性ホルモン(テストステロン)が減少し、心身にさまざまな不調が現れる状態です。
女性の更年期に比べて知られていませんが、近年、医学的にもその存在が明らかになってきました。
中高年就労男性のおよそ 約10%が更年期障害に苦しんでいます。
テストステロンは40 歳代で約 10%,50 歳代で約 20%,60 歳代で約 50% が境界領域以下になることが知られており、30代から緩やかに減少を始め、特に慢性ストレスや生活習慣の乱れがその減少を加速させます。
この症候群の中心的な原因は、男性ホルモン・テストステロンの低下です。
テストステロンは、筋肉や骨、心のバランス、性機能に深く関わるホルモン。
その分泌は、脳の視床下部→下垂体→精巣というホルモンの連携システム(HPG軸)によってコントロールされています。
加齢やストレスによりこの軸がうまく働かなくなると、テストステロンが減少し、さまざまな不調が起こります。
遊離テストステロン(Free-T)の値を確認します(8.5pg/mL未満が目安)。
「AMSスコア(Aging Males’ Symptoms Scale)」というスクリーニングテストがあります。
西洋医学の治療に加えて、鍼灸は補完療法として有望な選択肢となり得ます。
腎兪、命門、関元、足三里、太渓、神門 など
これらは東洋医学でいう「腎虚」や「肝鬱気滞」の改善を意図した配穴です。
注意: 鍼灸は医学的な治療に代わるものではなく、医師の診断と併用する形で活用するのが理想です。
男性更年期障害(LOH症候群)は、明確なホルモンの変化に基づく病態です。
それは同時に、心身のバランスを見つめ直すチャンスでもあります。
もしあなたや大切な方が思い当たる症状を感じていたら、まずは気軽にご相談ください。
医師との連携のもと、鍼灸による丁寧なサポートをご提案いたします。
「死」はすべての人にとって避けられない現実でありながら、その本質について深く考える機会は意外に少ないかもしれません。
このシリーズでは、世界の構造、心と世界の関係性、意味の生成、他者との応答性などを仏教とユング心理学、そして「易」の視点から探求してきました。
それらの議論を踏まえると、「死」という出来事も単なる“終わり”ではなく、「意味の構造の再編成」として捉え直すことができるのではないでしょうか。
仏教では、「死」は「自己」の終焉ではなく、五蘊(色・受・想・行・識)の一時的な離合集散にすぎません。
縁起の教えによれば、存在するすべての現象は、無数の因縁によって生じ、因縁が尽きれば滅していきます。したがって「私が死ぬ」というとき、そこには「一貫した実体としての私」が滅ぶのではなく、「条件的な構成体」が一時的に終息するという意味が強いのです。
『阿含経』には、釈迦が「人は五蘊によって構成される。五蘊は無常である。ゆえに苦しみである」と述べています。これは、死を恐れることよりも、無常を理解し、執着を手放すべきことを教える言葉でもあります。
カール・グスタフ・ユングは、「死」を単なる終焉としてではなく、個性化(インディヴィデュエーション)の過程の完了とみなしました。
個性化とは、無意識と意識を統合し、真の自己に至る過程です。その道のりを経た魂にとって、「死」は崩壊ではなく、「意味の統合点」なのです。
ユングはまた、死後の世界についても言及しており、『赤の書』や晩年の著作には、象徴的な死後のビジョンが描かれています。そこでは「魂」が集合的無意識と再結合し、新たな意味の場に入っていくという構想が示されています。
前回までの議論では、「世界は意味と関係性のネットワーク」であり、「私の問いに応答する他者」が世界の本質であるという視点を得ました。
この観点から見ると、「死」とは「他者との関係の断絶」ではなく、「関係の形式が変化する」出来事とも言えます。
こうした経験は、死後も関係が「意味の場」において存続していることを示唆します。
仏教では、宇宙もまた生滅変化するものとされています。『起世因本経』では、世界が生成し、滅し、再び生成するという無数のサイクルが語られます。
これは、世界そのものも「意味の連鎖の中で生まれ変わる存在」であることを示しています。
一方で、ユングの集合的無意識の概念からは、「すべての魂がつながる共通の場」が想定されており、死後も意識のかけらはこの場に留まり続けると考えられます。
死ぬのは「私」ではない。仏教の無我の教えは、この問いに答えています。
「私」というものは、五蘊の一時的な結合にすぎず、それが終息すれば、そこに「私」は存在しない。
しかし、ユング心理学的には、個としての「私」は死を迎えても、「普遍的な意味」へと昇華される道が残されているとされます。
つまり、死とは「小さな私」が終わり、「大きなつながり」に回帰する運動とも言えるのです。
死者が語る、死者が応答するということはあるのか? これに対し、仏教は慎重であると同時に、開かれています。
例えば、『ジャータカ物語』では、過去生の記憶が語られ、死後も縁によって新たな生が始まることが描かれます。
また、ユング心理学では、「死者の夢」や「亡き人との内的対話」は、無意識からの意味深いメッセージとして扱われます。つまり、「死者は象徴的に応答する」のです。
死とは何か。それは「存在の終わり」ではなく、「意味の変容」です。
仏教は「すべては縁起によって生起し、また滅する」と教えました。その観点では、死もまた自然の一環であり、恐れるべきものではありません。
ユング心理学は、「死」を魂の統合と再編成の契機ととらえ、象徴的な完成として尊重しました。
こうした視点を持つことで、私たちは死を通して生を深く理解し、生の中に死を抱きしめることができるようになるでしょう。
そして最期のときにも、世界が私にどのように“応答”してくれるか──それを見届けるまなざしを、私たちは持つことができるのです。
本シリーズを通して私たちは、「世界とは何か?」という根源的な問いに、多角的かつ深層的に取り組んできました。
ユング心理学の共時性、上座部仏教アビダンマの瞬間的な世界生成、『アガンニャ経』に描かれた宇宙神話、そして『易経』の関係的宇宙観──それぞれは異なる文化的背景を持ちながらも、実は「意味の場」として世界を捉えるという一点において交差していました。
現代人はしばしば、世界は客観的に「そこにある」ものだと考えがちです。しかしアビダンマの心理哲学は、世界は刹那ごとに「心」によって立ち上げられる現象であると語ります。ユングはこの「心が現実を意味で貫く力」を共時性として捉えました。
つまり私たちは「与えられた世界」に住んでいるのではなく、心の働きによって意味づけられた世界を、その都度生きているのです。
『アガンニャ経』に描かれた天地開闢の物語では、世界の始まりは「欲望」から分離が生まれ、自己と他者が現れたとされます。それはユング心理学における「個性化過程」とも通じます。
この宇宙に多様な存在があるのは、分かたれたもの同士が関係性の網の目を織りなし、再び意味を回復していくためなのかもしれません。つまり、存在は「孤立」しているのではなく、常に他の存在との間で響き合いながら世界を織り成しています。
シリーズ中盤で扱った「他者」の問題は、とくに哲学的に重要な論点でした。
私の問いに応答する他者とは、私と意味を共有できる場にいる存在です。これは人間に限らず、動物、自然、夢、出来事までもが含まれます。
逆に、応答しない他者とは、私の「意味の場」にまだ繋がっていない存在です。しかしそれは「敵」や「無関係なもの」ではありません。むしろ、応答しない他者の存在があるからこそ、私たちは「意味とは何か」を問い続け、世界を広げていけるのです。
「病気」という現象も、もはや単なる肉体の故障としてだけでは捉えられませんでした。アビダンマ的には、病は心と身体の微細な因果の集積であり、心の偏りや執着が引き起こす現象として理解されます。
ユングにとっては、病はしばしば魂の危機であり、より深い意味に目覚めるための呼びかけでもあります。病気を「意味の転換点」「魂の調律」として受けとめるとき、それは単なる敵ではなく、自己と世界を見直す貴重な縁となり得るのです。
死は、生の終わりではありませんでした。むしろ、生の意味がもっとも純粋なかたちで問われる瞬間です。
アビダンマにおいては、死とは一つの心の流れが終わり、次の生の条件を引き継ぐ「断絶なき変化」であり、輪廻の一環とされます。
ユングは、死を「個性化の最終段階」、魂が集合的無意識に帰還する過程と見ました。
いずれの立場においても、死は「無」に還ることではなく、関係の変容です。それは、心と世界のつながりが別のレベルに移行することを意味しています。
本シリーズのすべての議論を貫く最大の洞察は、以下の一文に集約されます。
世界とは、客観的に存在する「もの」ではなく、
主観と他者とのあいだで生成される「意味の場」である。
私たちは日々、無数の出来事と出会いながら、そこに意味を与え、世界を織り直して生きています。問いを発するとは、その世界に向かって意味を差し出すこと。
そして、世界が応答するとは、その問いがつくった縁に、他者が何らかの意味をもって応じること。
この世界は、誰かが一方的に作った舞台ではありません。
私たちは常に「意味」の共同生成者として、この世界を共に生き、編み続けているのです。
病も、死も、他者との出会いも、そのすべてが「意味のネットワーク」のなかで動いています。
そして、そのネットワークに耳を澄ませるとき──世界は、確かに私たちに応答しているのです。