稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

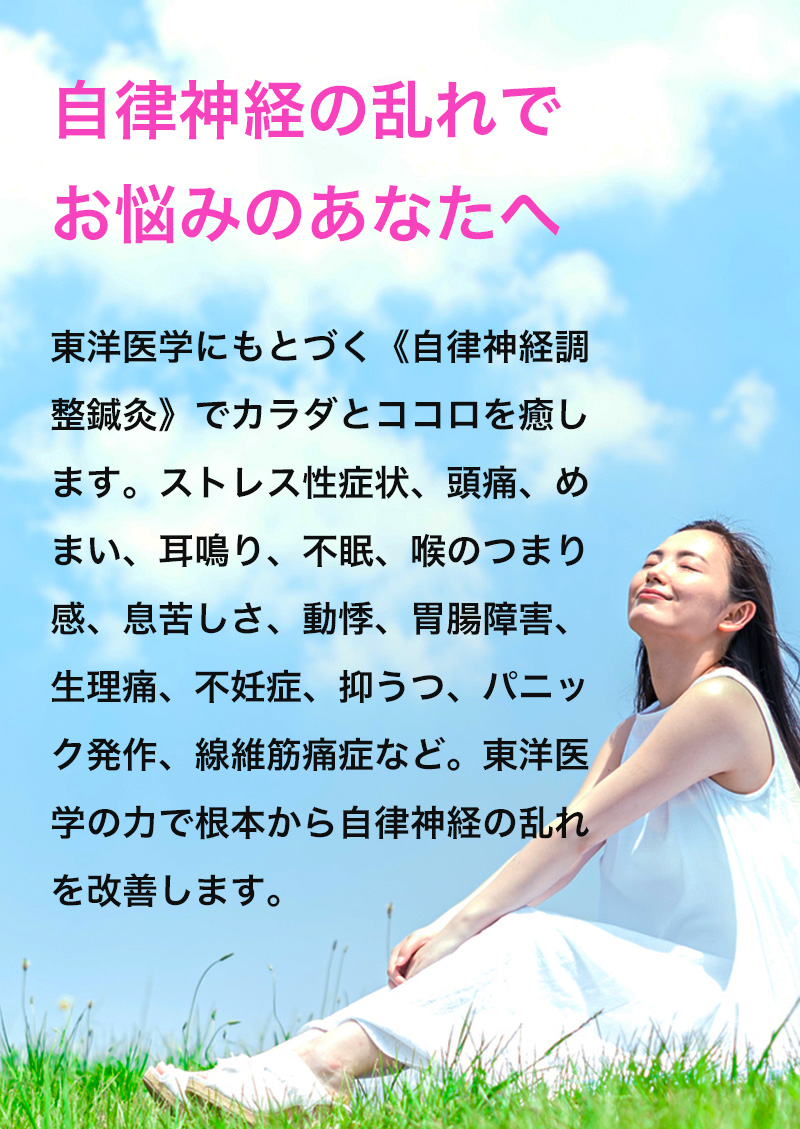

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
自律神経が乱れてめまいや腹痛、吐き気、カゼなどの症状を訴える方が増えてきています。
今年の夏は処暑を迎えるまで異常な暑さでした。今はだいぶ気温が落ち着いてきましたが、夜でも30度を超える日が続き、熱帯夜で睡眠不足になっていた方も多かったでしょう。
このような状態ですから体調を崩すのも無理はありません。寝不足で体力が落ちている上に仕事や家庭の仕事に追われ、クーラーや冷たい飲み物で体の外側と内側から冷やしますから体が芯から冷え切り、自律神経も乱れます。
冷えは体を強張らせて自律神経を乱しますが、特に腰部や下肢が冷えて強張ると吐き気や腹痛、下痢などを起こし、背中だとカゼや咳き込みになり、首だとめまいや頭痛を起こしやすくなります。
根本は体の冷えですから、これらの症状を治めるには体を温めることが大切になります。体の冷えは足湯や脚湯、半身浴が適しています。部分浴のやり方はこちらを参考にして下さい。
このような部分浴を続けることで体の冷えが取れ、自律神経が整うことで様々な症状も治まってきます。しかし、しつこい症状には専門家による加療が必要になります。そのような場合にはお近くの鍼灸院にご相談されると良いでしょう。
まだまだ暑いですが、風が吹くと秋の気配を感じさせますね。
明け方などは気温が下がってきていて、体を冷やしてカゼをを引いている方が出てきています。
昼間の暑さでつい冷たい物を飲んで胃腸を冷やしてきたことも影響しているようです。
このような冷えには朝の足湯が最適です。
こちらの記事を参考にして、足湯で冷えを解消されると良いでしょう。
秋口のめまい・腹痛・吐き気・頭痛・カゼなどの症状は「冷え」が原因
ここのところ当治療室でもカゼを引いている方が目立ちます。症状は2種類あり、咳き込み症状かお腹を下す症状のどちらかです。
診察すると体が冷えている方がほとんどです。気温が上がったことで油断して薄着になり、冷やしてしまったのでしょう。また寝るときも薄着になることで、明け方の冷えの影響を受けているものと思われます。
このような場合は脚湯が効果的です。やり方は膝立ちで湯船に入り、下腿がすべて浸かるくらいお湯を張ります。温度はガマンできるギリギリの温度です。
時間は6分間。1日にできたら2回、寝る前と起き抜けに行います。これを3日間繰り返すと体の冷えはかなり抜け、カゼの症状も楽になるでしょう。
梅雨時期の冷えは夏バテにもつながります。この時期にしっかりと対策をして、体に冷えが残らないようにしましょう。