稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

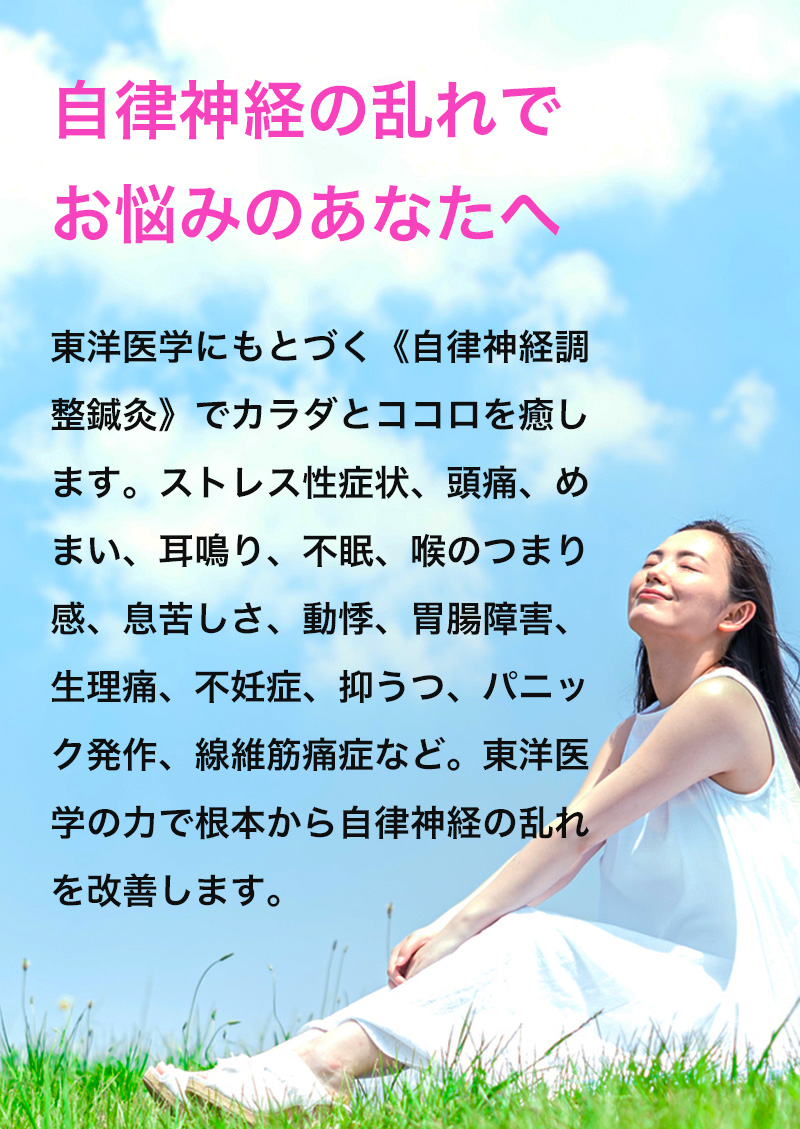

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
1年前に父親が死亡し事業の引き継ぎなどの心労から胃の不快感が起こる。胃カメラで器質的な病変なし。動悸や不安感 、首の痛み もある。六君子湯を服用すると楽になる。鍼 で神経系と胃の経絡を開く。第2診後に95%回復したとのこと。
仕事のストレスから動悸や睡眠障害 に。現在は休職中。心療内科 で投薬治療するも今ひとつ。鍼灸治療 で神経系と胃腸系の経絡を開く。第3診で症状がほとんど改善され柔和な表情に。体質的に胃腸が弱く、腸は不安感情と関連が深い。
臨月になっても子宮口が開かず産まれる気配がない。来週に促進剤を使う予定とのこと。診てみると頭の使い過ぎで骨盤が硬張り、骨盤の開閉運動が阻害されていた。鍼灸で頭と骨盤を調整したところ翌日の夜に陣痛が起こり、次の日に無事女の子を出産された。