稲森 英彦 Hidehiko INAMORI
プラナ松戸治療室代表
【略歴】
東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。
1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。
2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。
現在(2025年)臨床歴27年。

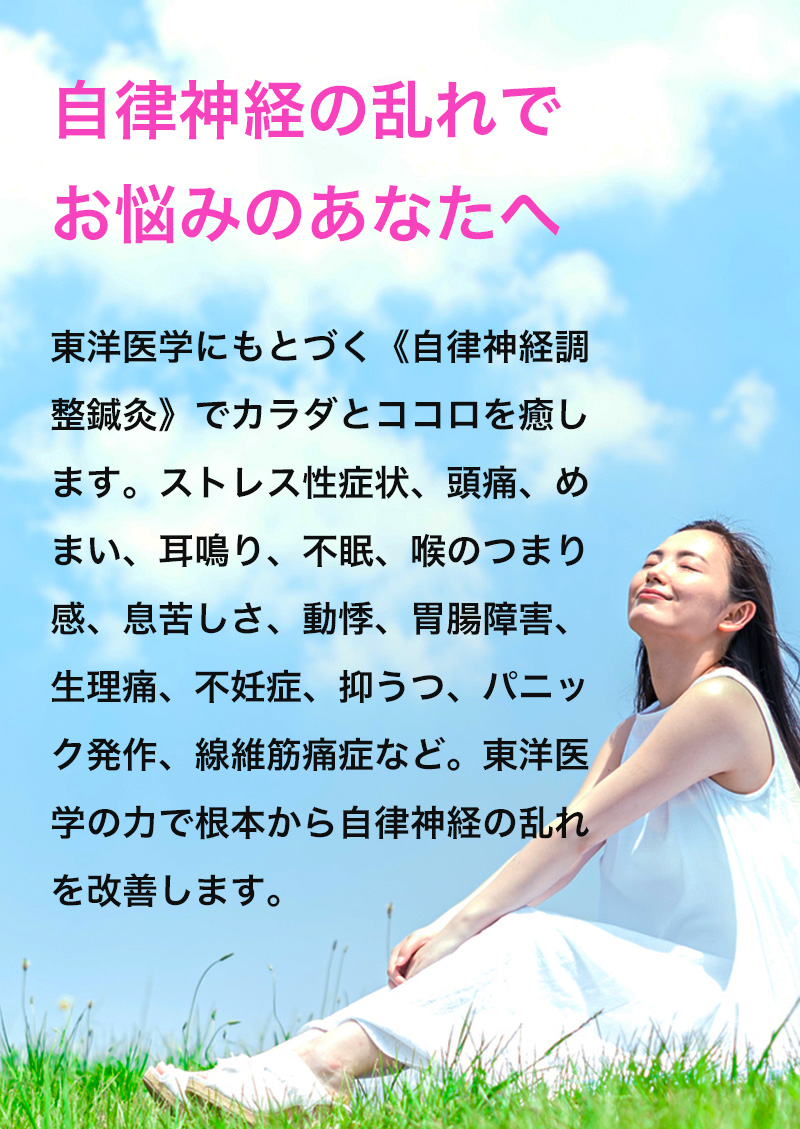

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。
詳細はコチラ
頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。
詳細はコチラ
息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。
詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。
足がつった時のような痛みが首から肩甲骨の奥にかけて断続的に起こるという患者さん。ペインクリニックで ブロック注射をするも全く効果がないという。頸椎、胸椎、上腕を鍼で調整。帰りの電車内で痛みが1/3になる。2診目も同じ処置を行った後完治した。
息苦しさ、動悸、めまいの患者さん。診ると背骨周りがガチガチに硬くなり ストレス反応が強く出ていた。昨年から実父と同居することになり強くストレスを感じているという。頸椎、胸椎、呼吸器と関連の深い 骨盤を鍼で調整。症状がなくなり「スッキリした(笑)」と帰っていかれた。
1ヶ月以上咳が止まらない患者さん。新型コロナの PCR検査は陰性。その他の血液検査も異常なし。不安から来る体調不良と診断された。当治療室で診ると胸郭と上部胸椎に強いこわばりがあった。鍼灸でこれらを調整。初回の治療後に70%改善。2診後に咳は止まった。